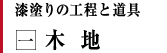
漆を使ったものでピンとくるものは、器などの漆器類じゃないでしょうか。 この漆器。日常生活での使用が本来の目的なので、水に濡れることや、 多少手荒に扱うことなどの状況が当然ながら塗装上必要な条件といえます。

|
|
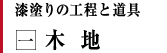
漆を使ったものでピンとくるものは、器などの漆器類じゃないでしょうか。 この漆器。日常生活での使用が本来の目的なので、水に濡れることや、 多少手荒に扱うことなどの状況が当然ながら塗装上必要な条件といえます。 |

|
|
|
漆器塗装では、堅牢性に優れた「本堅地塗り(ほんかたじぬり」が塗装法の代表です。
名称として漆を銘打ってあっても、漆ではない塗料を使用しているものも少なくありません。
仮に表面にだけ漆が塗ってあったとしても下地や素地(木地)が半端なものなら無意味。
本堅地塗りはその表面の漆に意味があるのではなく、
素地の十分な乾燥と何層にも重ねて漆下地を塗ることで、何十年にもわたる堅牢性が生まれるのです。
仏壇も漆器ほどの完全防水性の必要がないとはいえ木地と下地が重要です。 現在、下地処理を施してある合板などを使用している仏壇も多くありますが、 耐久面の予測がたたないので、小宮仏壇店は昔ながらの木地「杉」を主に使用します。 十分に乾燥させてあるとはいえ経年による痩せのない木はありません。 そのために相応の下地を行い、最後に漆を塗ることで隠蔽(いんぺい)性を高め、 何十年にもわたる堅牢性が保たれるのです。 仏壇は産業としての歴史の古さもあり、 一般的に「木地屋」「彫師」「塗り屋」「蒔絵師」「金具屋」に分業されています。 木地屋の仕事は、一般的な塗装よりもはるかに厚い塗りを念頭に置いた木地造りが 家具などとの大きな違いでしょう。 |