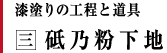
漆に欠かせない下地「砥乃粉(とのこ)」。 さらに堅牢性のある「地乃粉」は布を貼っていない平面部分に使います。 砥乃粉は黄土を焼いて作った粉で、その昔は砥石を切り出した粉を集めたものらしく、 その由来から砥乃粉という名称なったのでしょう。

|
|
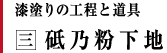
漆に欠かせない下地「砥乃粉(とのこ)」。 さらに堅牢性のある「地乃粉」は布を貼っていない平面部分に使います。 砥乃粉は黄土を焼いて作った粉で、その昔は砥石を切り出した粉を集めたものらしく、 その由来から砥乃粉という名称なったのでしょう。 |

|
|
|
しかもこの砥乃粉は漆下地のみならず古くは役者の化粧下地に使われていたとゆう話もあります。
それだけに粒子は非常に細かくファンデーションのような感じです。
昔の大工仕事では柱に手の油分が着くのを防ぐために砥乃粉をすりつけたりもします。
このように砥乃粉そのものは単なる粉で下地としての役目は果たさないので、 砥乃粉にボンドと水を練り混ぜ接着性を持たせます。 昔ながらの方法だと生漆もしくはニカワを混ぜるわけですが、 仏壇の下地面積からすると生漆は価格的にも現実的ではありませんし、 ニカワは現代の接着レベルからすると弱く保存もきかない。 保存・強度・耐久面でも遜色がないのでボンドを合わせています。 しかしボンドと水は基本的に分離する性質があるので、 細かい分量設定と気候に応じたボンド種類の選別が必要となります。 こうやって混ぜた砥乃粉は刷毛塗り用の液状のものと、ヘラ付け用のペースト状のものと2種類練り、 まず刷毛塗り用で塗って乾かし塗って乾かしと2回塗り、 必要な部分には地乃粉と砥乃粉下地を混ぜたものをヘラ付けし、さらに塗って乾かし、 全体を砥石で軽く慣らした上でヘラ付け用をヘラ付け乾燥ヘラ付け乾燥とこれも2回施します。 十分乾燥したものを砥石で水研ぎし砥乃粉下地が終了です。 砥乃粉とはいえ十分堅いので、ヘラ付け段階である程度平らになっていないと この水研ぎで苦労するはめになります。 一連の砥乃粉下地作業は、時間的にも体力的にも一番手間のかかる作業です。 |
|
|
 砥乃粉  ヘラ付け用に練った砥乃粉下地 |
砥乃粉下地いろいろ
生漆と砥乃粉を混ぜた下地は「錆(さび)」。 糊と砥乃粉を混ぜた下地は「泥地」。 ニカワと砥乃粉を混ぜた下地は「加乃地」「仏師地」。 ニカワと地の粉を混ぜた下地は 「万造地」。 漆器は堅牢性と防水性を必要とするので、通常「錆」を使います。 漆と砥乃粉の相性が良い理由はこのへんにあり、エマルション塗料である漆は、 その吸油性により空気中の水を含んだ砥乃粉と混ざることで、 漆独特の湿度による自然乾燥状態になります。 これにより漆の堅牢性が下地段階を経て十分に発揮できるわけです。 |
|
|
 次の工程へ 次の工程へ
塗りの工程--| 1.木地 | 2.布張り下地 | 3.砥乃粉下地 | 4.中塗り | 5.上塗り | 6.摺り漆 | 7.金箔押し | |