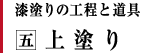
これまで様々な工程を経てきましたが、この上塗りが塗りの最終段階です。 上塗り仕上げの場合を「塗り立て」と言います。 そもそも漆は乾燥に時間がかかり、厚みの違いで縮み、 ホコリは大敵とゆう非常に扱いずらい塗料です。 それだけに何より技術を要する塗料と言えるのでしょう。
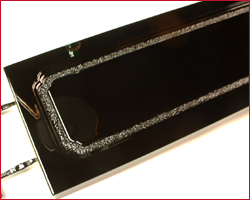
|
|
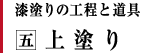
これまで様々な工程を経てきましたが、この上塗りが塗りの最終段階です。 上塗り仕上げの場合を「塗り立て」と言います。 そもそも漆は乾燥に時間がかかり、厚みの違いで縮み、 ホコリは大敵とゆう非常に扱いずらい塗料です。 それだけに何より技術を要する塗料と言えるのでしょう。 |
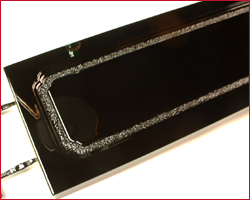
|
|
|
まず漆の塗装作業は、漆を「濾す(こす)」ことからはじまります。
3枚の和紙を交互に折り重ね6層にしたうえで漆を包み、それを濾し器で濾します。
和紙の両端をねじり、そこから流れ出る漆を塗りに使うわけです。
漆には色(朱・黒・透)の違いのほかに、呂色用・中塗り用・箔下用・艶消し・摺り漆など、
さらに細かく分類すると十数種になります。また漆それぞれには早口・遅口・不乾燥など
気候に応じた乾燥速度別の種類がありますが、これをそのまま使うことはほとんどなく、
塗る日の気候に合わせて乾燥速度は自分で調合して使うのが通常です。
ホコリは漆の大敵なので、衣服のホコリはしっかり落とし、 できるだけ漆を塗る部屋では動きまわらないように作業します。 どんな塗料の塗装でもホコリは大敵なのですが、特に漆はその乾燥速度が 遅いこともありホコリ自体が漆を吸い込んで、乾燥時にはポツポツと目立つからです。 乾燥速度を速めると漆特有の乾燥時表面の縮みが出やすく、 薄く塗れば縮むことを回避できるものの、 今度は刷毛筋や塗りムラが出やすい状態となります。 逆に乾燥速度が遅ければ塗りの表面はそれだけ平坦になりますが、 それだとホコリが付着する可能性が高く、なによりその後の仕事が進まない。 この乾燥のバランスを塗る日の湿度・温度によって漆の調合を変えるわけです。 漆は粘性が塗装面の肉持ちの上で重要なのですが、ゆえに縮みも出やすい。 縮みとゆうのは塗りの厚みによる表面の乾燥速度と内部の乾燥速度の違いから出てしまうものなのです。 やむなく入ったホコリは竹を薄く細く尖らしたもので手早く取り(節とり)、 塗り上がったものを「漆ムロ(漆ブロ)」に入れて乾燥させます。 |
|
|
 漆ムロ |
塗り場と漆ムロ
漆器塗りは床に座って作業しているイメージがありますが、 仏壇塗りは椅子に座るか立って仕事をします。 塗りの対象が大きく必然的に体の移動量が大きくなるので、 このほうがホコリ付着が格段に減るわけです。 漆はその成分にある酵素が作用して硬化する特殊塗料。 酵素は水分で酸化を促進するので「漆ムロ」の中は高湿度の状態です。 冬場などの乾燥期には「漆ムロ」の中に水を撒いて湿度を作り出します。 |
|
|
 次の工程へ 次の工程へ
塗りの工程--| 1.木地 | 2.布張り下地 | 3.砥乃粉下地 | 4.中塗り | 5.上塗り | 6.摺り漆 | 7.金箔押し | |